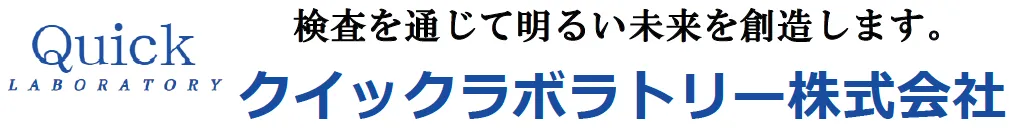〔公益社団法人東京青年会議所渋谷区委員会〕が主催、〔東京都〕などの後援で開催された
性教育事業「SHIBUYA LIFE CANVAS 2025 in渋谷道玄坂教会」に参加しました。
東京都も梅毒の感染拡大ストップに注力している中で開催された今年のイベントで、郵送検査事業者として啓蒙活動を担当、ステージでの発表も行いました。
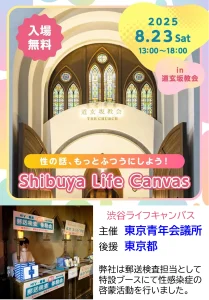
ステージでの発表内容
本日は『郵送検査』と『性感染症』について、お話しいたします。
皆様におかれましても郵送検査を利用されたことがある方がいらっしゃると思いますが、郵送検査というのは、希望する検査キットを購入し、検体採取を自身で行い、採取した検体を返送(郵送)して、検査結果をウェブサイトで確認する検査システムです。
国内で性感染症の郵送検査が始まって 28年ほど経ちますが、今では、ずいぶん身近な存在になってきているように思います。
昨年(2024年)のHIV検査を例にとると、全国保健所のHIV検査数がおよそ11万件に対して、郵送検査は、約13万件にのぼっています。
郵送検査がここまで広まった理由は、簡単にいえば『自分の都合に合わせて検体を返送できて便利だから』という『受検者様本位の検査』という部分があると思います。また、誰にも知られずに検査できる、または、人と対面せずに検査できるから恥ずかしくないといった理由も大きいように思えます。
医療機関での検査と違う所は、郵送検査は自分自身で検体を採取します。『自己採取』というと、大変なように思えますが、説明書通りに行えば、誰でも簡単に採取できますし、自己採取は医師の採取と同等の精度であることも検証によってわかってきています。
郵送検査も医療機関も、国が承認した検査試薬を使っており、専門の検査技師が検査室で測定をしていますので、検査精度という観点では全く同等といえます。郵送検査は疑わしい検査なのではないかと思われる人がいらっしゃるかもしれませんが、安心して郵送検査を活用してほしいということが私の話の1つ目です。
次に具体的に4つの性感染症のお話をします。まずは『クラミジア感染症』と『淋菌感染症』です。それぞれ違う病気ですが、共通点が多いので、まとめて特徴をお話しします。
・性器に感染し、男性の場合、比較的症状は出やすいが、女性は無症状なことが多く、感染していても気が付きにくい特徴がある。
・感染者との(コンドームを使用しない)1回の性交渉で感染する確率は30~40%程度である。
・性器のほかに『のど』 や 『肛門』 にも感染する。
・『のど』や『肛門』から性器にも感染する。特に女性の『のど』から男性の性器への感染が多い。
・一度感染が成立すると自然治癒はしない。
・治療して治っても 再感染する。
無症状であることが多く、感染しても放置すればよいのではないかと思うかもしれませんが、放置すると特に女性の場合、クラミジア・淋菌が上行性感染といって、子宮から腹腔内に侵入し腹膜炎や肝臓の周りに炎症を起こして、激しい腹痛を訴え、救急搬送されるようなこともあります。さらに卵管や卵巣に炎症を起こして子宮外妊娠を招いたり、不妊症の原因になります。
男性の場合は 精子を貯蔵する精巣上体というところまで炎症が広がっていってしまうことがあります。つまり、放置すると、からだの中で炎症が広がっていってしまいます。だからこそ早期発見、早期治療が大切です。
次に『梅毒』です。梅毒に感染すると、しこりや発疹ができると言われていますが、梅毒の基本の病型は潜伏梅毒(無症状)と覚えてください。
仮に梅毒で発疹(ボツボツ)ができてもそれを見てすぐに梅毒と結びつけることが難しく、検査をしないとわかりません。梅毒は治療しても何度でも感染するため、その都度、検査が必要になってきます。
長期間放置すると、心臓や血管の病気、神経麻痺、認知症のような症状がでることがあります。また、放置しなくても早期神経梅毒が知られており油断できません。
梅毒で最も注意をしなければならないのが『先天梅毒』です。妊婦さんが梅毒に感染するとおなかの赤ちゃんも梅毒になってしまいます。
先天梅毒は、様々な病気を子どもに背負わせてしまいます。何としても防いでいかなくてはなりません。
最後に『HIV感染症』です。感染して放置すると免疫力が低下してゆきます。感染しても基本は無症状ですから、節目節目に検査が必要です。
2024年には1000人の感染があって、そのうち3割がエイズを発症している状態です。
エイズを発症してしまうと、発症前と比べて治療が難しくなるため、早期に発見し、早期に治療することが重要です。
以上、4つの性感染症のお話をしましたが、放置してよい病気は一つもありません。これら4つは性感染症の中で特に重要ですので、ぜひ覚えておいて検査を行ってほしいと思います。また、感染の予防にはコンドームが有効ですので、ぜひ活用してください。
最後の話になりますが、先ほど話をした『クラミジア感染症』と『淋菌感染症』は、どれくらいの人が感染しているかというお話をします。郵送検査を利用された方々におけるお話です。
わかりやすくお話をすると、女性の受検者様の場合、100人の集団として考えた場合、性器にクラミジアが感染している人が13人、のどにクラミジアが感染している人が6人、性器に淋菌が感染している人が3人、のどに淋菌が感染している人が5人となり、100人中27人、よって3.7人に1人がクラミジアまたは淋菌に感染していることになります。
男性の受検者様の場合、同じく100人の集団として考えた場合、性器にクラミジアが感染している人が8人、のどにクラミジアが感染している人が1人、性器に淋菌が感染している人が2人、のどに淋菌が感染している人が3人となり、100人中14人、よって7人に1人がクラミジアまたは淋菌に感染しています。
梅毒は受検者全体で見た場合、1,000人に4人程度、HIVは10,000人に2人程度です。
受検者の方々のクラミジア・淋菌の陽性の割合(陽性率)は毎年横ばいの状況にあり、すごく増加しているわけではないけれども、減少してゼロになる様子もありません。すごく増えていない理由は受検者の方々が定期的に検査をしているからかもしれません。けれども、検査をしているのになぜ陽性の割合は減っていかないのでしょうか。これはなかなか難しい問題です。
私の個人的な考えを言うと、性的な接触を持っている当事者が両者ともに感染していないという状況を作っていくことが大切であると思っています。
また、お互いに『相手に感染させない』という考えを持つことが大事に思います。
相手に感染させないようにするには、自分の感染に無関心ではいられないと思いますし、相手のために検査を受けようという発想になります。
そのように一人一人が思い始めると、出会った二人がともに陰性という状況が増えていき、陽性の割合も減少していくように思います。
性感染症の感染を減らすにはどうしたら良いのかを皆さんもぜひご自身で考えて実践していただくとよいと思います。
以上、話を終わりにいたします。ご清聴ありがとうございました。